この記事では、週刊少年ジャンプ2025年38号に掲載された「あかね噺」の第170席「三明亭の型」の感想と考察を書いて行こうと思います!
前回の振り返りは下の記事になります!
三明亭からしの演目は「猿まね」。審査員ブギウギ真田は「こんな古典落語は存在しません」と言う。からしが演っているのは古典の世界観をベースに作った新作落語。現代の話を古典に作り替えた偽りの古典── ‟擬古典”だった!
そして何と言ってもアニメ化ですよね~!
声優陣は林家木久彦師匠から稽古を受けて臨んでいるみたいですね。そして沢山の人が落語と「あかね噺」に対して熱い情熱を注いで制作に励まれているそうです。それが今週の番外編で描かれていますよ!
ホント楽しみです♪
何故其れを落語でやるの?
人気役者の不倫の噂を聞いた読売の定吉が真実を追いかける。調べるに当たって貰ったお金(お足)をすぐに芝居見物に使ってしまう── 三明亭からしの噺に会場もウケていますね。序盤でガッチリ掴みました。
そこに審査員ブギウギ真田が1つ疑問を呈します。
何故其れを落語でやるの?
多様な新作落語が作られ、落語の裾野が広がるのは大歓迎。しかし「コント・漫才・映画・マンガ・アニメ・小説」と様々な表現方法がある現代において、創作したものを「落語」でやる意義は何なのか。
三明亭からしにとって落語とは何なのか?
これが1つポイントになりそうですね。
前回で描かれているんです。
では今、ブギウギ真田の問いに三明亭からしは答える事ができるのか。ここなんでしょう。落語でやる意義を見つける事ができたのか。彼にとって落語とは何なのか。
それを探しながらの修行だったようです。
‟破邪顕正”三明亭円相
からしも師匠である三明亭円相に「落語とは何なのか」を質問していたようです。まだ弟子入りしてすぐの頃でしょうか。答えてもらっていますね。
落語とは儂である
儂になれ
それが至上の道だ
円相師匠には落語界における「伝統の象徴」としての自負があるんでしょうね。そしてそれは「古典落語こそ落語」であるという考えが基礎にあると思われます。だからこそ聞く者に‟古典かくあるべき”と思わしめる円相師匠は「落語こそ儂である」と言う。
「儂になれ」とは「儂の芸を受け継げ」って事かな?
三明亭円相は六代目。そして昭和・平成・令和と三つの時代を大看板として生きた男。「三明亭円相の芸」は相当古くから継承されて来たのが分かります。それをからしに受け継いでみせろと言っているんでしょう。
それが「至上の道」である。
からしにしても「擬古典をやるにも アレを理解するにも古典のスキルはマスト」と考えており、古典の真髄を見抜いてみせようと円相師匠の高座を袖で勉強しています。
貴様には‟了見”は掴めない
古典の真髄を見抜こうと意気込む三明亭からしでしたが、落語の稽古は入門して3-4ヵ月まで。そこからは踊りなどの余芸の稽古と、修行と言う名の雑務。それも確定申告まで(笑
文句も言わずこなしていますが、それが‟了見”というものを掴む為だと分かっていたから。やり切らない掴めないと理解した上での事だったんですね。
今回の「猿まね」の演目でいくと、円相師匠から命じられる雑務をこなしてこそ、定吉の心情に寄り添えるって事なんでしょうね。京都でしか買えない菓子を買う為にお金をもらってます。これも今回の噺に繋がりそう。
しかし、からしは賢すぎたんです。
一歩引いて物事の全容を捉え、要点を掴んで事に当たるから失敗しない。それは素晴らしい事なんだけど、その賢さは枷ともなる。‟了見”を掴むには没入する事が必要。一歩引いて物事を見てちゃダメ!
貴様に‟了見”は掴めない
これは完全に盲点でした!
なるほどなぁ~と。
了見と対を成す極意「三明亭の‟型”」
円相師匠が言うには、先代の五代目阿良川志ぐま(柏家生禄)こそが「最も愚かな男(最も‟了見”を極めた男?)」だそうです。つまり「志ぐまの芸」には‟了見”を極める必要がありそう。
それは阿良川あかねが成し遂げるのでしょう。
そして五代目阿良川志ぐまを「この儂に比肩すると認めた」円相師匠もまた‟了見”を掴めておらず、からしに対して「了見と対を成す極意」を授けると言うんですね。それは三明亭円相一門の相伝。
それは「三明亭の‟型”」と呼ばれるもの!
「了見」に対して「三明亭の‟型”」なんですね!
では、‟型”とは何なのか…
どうやら「心情」に対するものなんでしょうね。
そして、「古典」ですから能や狂言や歌舞伎に通じるものを感じます。やはり ‟型”というのは所作なんですかね。長い歴史の中で洗練され、受け継がれて来た演技・演出の様式。
それによって役の心情が掴めなくとも、その所作(型)で役の心情を見事に表現できてしまう。「中身の無ぇハリボテの芸」にさせない。
こういう事なのでしょうか?
そして次回になるのかな、高座のラストで冒頭のブギウギ真田の問いに対する三明亭からしの答えが明らかになりそう。「何故其れを落語でやるの?」「君にとって落語とは何だい?」の答えですね!
からしは見つけているんじゃないかな?
まとめ
阿良川ひかるの高座が3話に渡って描かれましたので、三明亭からしも同じく3話ならば次回がクライマックスになりそう。でも「猿まね」はまだ序盤っぽいんですよ。もう1話プラスかなぁ。
- ブギウギ真田の問い「何故其れを落語でやるの?」
- 三明亭円相曰く「落語とは儂である」
- ‟了見”を掴む為に文句も言わず修行と言う名の雑務をこなす三明亭からし
- 一線を引く賢さ故にからしは‟了見”は掴めない
- 三明亭の‟型”とは洗練させた所作か?
凄いものが見れそうな予感がします!
ありがとうございました!!





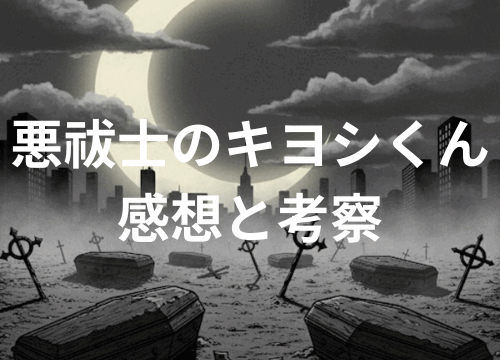

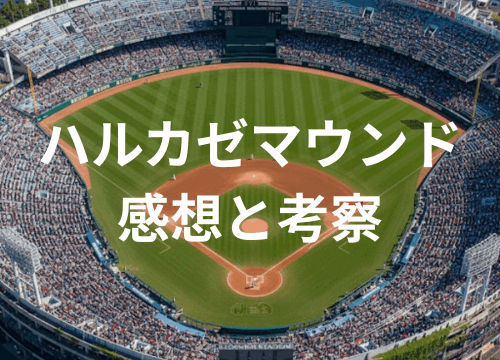


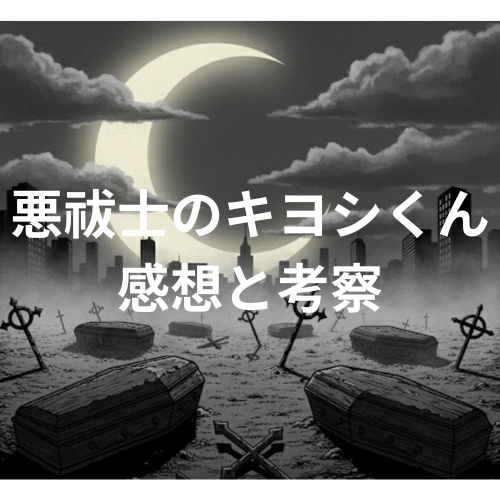
コメント