この記事では、週刊少年ジャンプ2025年36・37合併号に掲載された「あかね噺」の第169席「偽りの古典」の感想と考察を書いて行こうと思います!
前回の振り返りは下の記事になります!
阿良川ひかるの得点は276点で順位は第一位。椿家正明師匠も86点をつけ、落語家として高い技術を持っていると評価。湧き上がる感情に、自分が強くなった事を実感する阿良川ひかる。続いて三明亭からしが高座にあがります!
そして大ニュースですぞ!
ついに「あかね噺」のアニメ化が決定しました!
これは楽しみですよね~!
二ツ目に成ってから
冒頭 からしの過去が語られます。
何にだって攻略法があり、それを掴むのが得意だった彼。それさえ掴めば授業中に黒板に背を向け、またある時は教科書を立ててゲームをしながらお菓子を食べる。もう授業を聞く必要なんてない。
からしにとって「何でも出来る」というのがステータスであって、それを自身の拠り所としていたんですね。自己肯定感です。自分を信じるに足る根拠というものを積み上げて来た。
落語だって初めはそうでした。
2年連続で可楽杯で優勝。落語にしても攻略法を見つける事ができており、今年も楽勝と思っていたところに… 阿良川あかねが出て来るんでしたね。からしにとっては衝撃だったワケです。
あかねに負けて優勝を逃すのですが、それ以上に「攻略法云々どころか理解すら及ばない」という落語の奥深さに触れた事に衝撃を受けた。それを教えたのが阿良川あかねの落語。
この負けは決して受け入れてはならない。「何でも出来る」という、これまで自分を信頼し支えて来たものが崩れてしまう。そうなるともう今までの自分には2度と戻れない。そう直観するんですね。
そこで阿良川あかねの同門になるのを避けつつ、古典落語で有名な落語家は誰であるかを聞き、三明亭円相師匠の弟子になるんですね。それは全て阿良川あかねに勝つため。目指すのは圧倒的な勝利です。
阿良川ひかるに対して「どっかの誰かさんみたいにハンパに勝つ気はない」と言っていますが、これは「四人会選考会」での事を言っているんですよね。
合計点では阿良川ひかるの勝ちでしたが、「配信」の点数以外は阿良川あかねを上回る事ができなかった。これには阿良川ひかるも分かっていました。今度はぐうの音も出ないくらい負かすといってました(第73席)。
からしはそういうのは求めていない。
前座のうちはまだ。
二ツ目に成ってから阿良川あかねをボコしてやる。そう決めていての今だったんですね。ようやくやって来た舞台だったのです。彼は彼で並々ならぬ想いで瑞雲大賞に出場していた!
演目は「猿まね」
三明亭からしの演目は「猿まね」というもの。
あらすじは──
今や江戸一番の人気役者と言われる市村猿太郎。お内儀さん(妻)がありながら密通(不倫)しているという噂がある。それがお上の耳に入れば流罪にだって処されかねない。そうなりゃ江戸中が大騒ぎ。
それを聞きつけた「読売」(瓦版を読み歩きながら販売する仕事)の親方は、定吉に噂の真相を追いかけるべく指示を出す──。
ここからお題の「猿まね」にどう繋がるんでしょうね。その意味は「考えもなく他人を真似ること」ですけど。役者の名前に「猿」がついているのがキモなのかな?
それはそれとしまして。このストーリはですね。
- 役者
- 不倫
- それを追う記者
- 不貞一つで全てを失う
時を超えて現代とリンクしております。
まるでどこかで聞いた話なんですね。
こんな古典落語 存在しない
三明亭からしの演目を聞いている桐谷ほなみ(テレビプロデューサー)が「… こんな古典もあるんだ」と漏らします。どう考えても江戸時代のお話ですし、そう思いますよね!(僕もそう思いました!)
しかし、隣のブギウギ真田は「まちがってますよ」と。
こんな古典落語は存在しない
え?
漫才師であり「演芸案内人」であるブギウギ真田は約20年に渡って毎年300席、延べ6000席以上の高座を聞いて来たと言います。文献でのみ残される演目もよく知っているそう。
そんなブギウギ真田によると、三明亭からしの演目は古典落語ではなく「古典の世界観をベースに作った新作落語」だと言うんですね。これは驚かされました!!
擬古典
三明亭からしは、阿良川あかねに対して真っ向から芸で挑むほど脳筋(脳みそまで筋肉)ではないと言います。これまで通り戦略を練った上で戦いますって事ですかね。力任せで挑むなんてしない。
そして今回は「改作落語」(古典落語を現代に作り替える)という邪道ではいかない。それでは若者にはウケても‟うるさ方”には刺さらない(=正明師匠には評価されない)。
だから次は逆。
現代を古典に作り替える!
「現在性に紐づく共感」と「伝統芸能の世界観」とを兼ね備えた「偽りの古典」。この‟擬古典”というもので三明亭からしは瑞雲大賞で勝ちに来たんですね!
これはZ-1グランプリの高座もそうだったのかな?
物議を醸したんですよね!
おそらく今回と同じものなんでしょう。
Z-1グランプリの決勝でも‟擬古典”で勝負してたんじゃないかな。そして「こんなものは古典落語じゃない…」というのは、古典落語にこんな噺はないって意味だったのかも。
これなら「作品派」の椿家正明師匠もシッカリ評価すると思うんです。「改作落語」のように作品(古典落語)を崩しているワケじゃないからです。あとは噺(作品)が完成しているかどうかですよね!
これは面白い事になって来ましたね!!
ともかく「猿まね」という演目の続きが聞きたい!!
もう噺に引き込まれてるんだもんなぁ~。
まとめ
阿良川ひかるの高座の傾向から行くと、次回が演目の中編になりそうです。オチは更に次になるハズなんですね。正明師匠の表情が気になるので、そこはチラッとでも次回に期待ですね!
- あかねと勝負するのは二ツ目に成ってから
- 三明亭からしの演目は「猿まね」
- ブギウギ真田は相当な落語通だった
- こんな古典落語は存在しない
- からしが演っているのは「新作落語」
- 偽りの古典‟擬古典”
- Z-1グランプリ決勝でも‟擬古典”だった?
続きも気になりますが…
次号は表紙&巻頭カラーです!
ここでアニメ化の発表でしょうね!
ありがとうございました!!





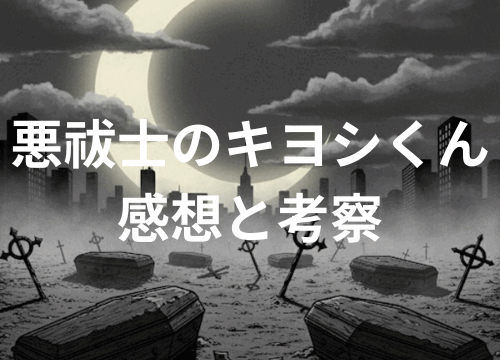

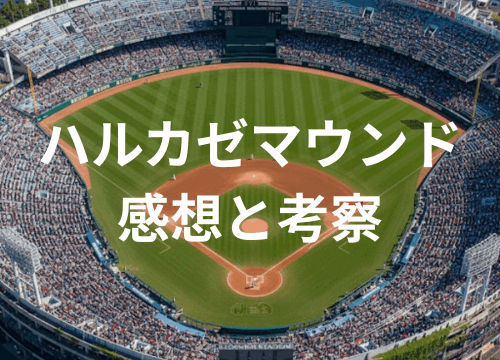

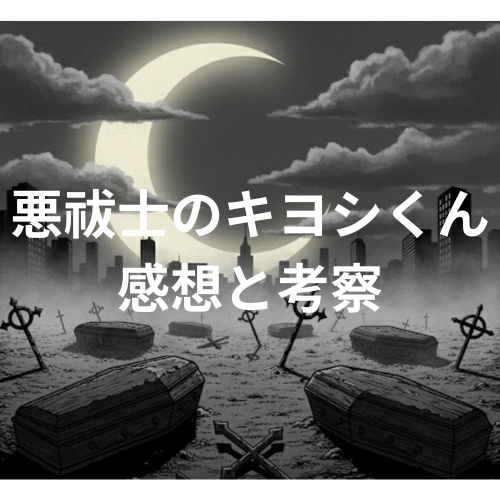
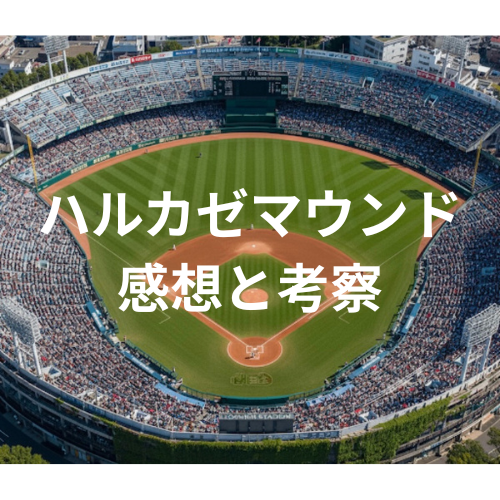
コメント