この記事では、週刊少年ジャンプ2025年39号に掲載された「あかね噺」の第171席「外形の極意」の感想と考察を書いて行こうと思います!
前回の振り返りは下の記事になります!
伝統の名の下に押し付けられる修行と言う名の雑務を文句も言わずこなしていた三明亭からし。その理由は‟了見”を掴むために必要だと考えていたから。しかし一線を引く彼には‟了見”は掴めないと語る円相師匠。
了見と対を成す極意「三明亭の‟型”」とは一体──!?
三明亭の型とは「外形の極意」
その人物の心持ちに成れば
自ずと仕草や言葉は変わる
内から滲むその根源
それが‟了見”
こう語る円相師匠は、からしに「狐の了見」は分かるか?と問います。これはもう正直に「分かりません」と答えるしかありません。動物の気持ちにまでは至れませんもんね。
狐でなくとも、どうしても心持ちが掴めない事は往々にしてある。あかねが花魁の了見を掴めずにいたようにです。ならばどうすれば良いのか。
外に目を向けろと
からし自身で答えに辿り着きます。
登場人物の「心持ち・心情(=内面)」がどうしても分からないのなら、「外(=仕草・姿勢)」に目を向けろと。これが「役ごとに体系化された作法」というものであって。
三明亭の型とは「外形の極意」である!
そしてまずは三明亭円相の所作の全てをさらい身体に叩き込む。その所作でもって観客の心を掴む! これこそが了見と対を成す極意だったのです。
志ぐま師匠は了見を掴めなければ中身のないハリボテの芸であり、それでは人の心は動かせないと説きました。三明亭の型にはそれを補って余りあるものがあるんでしょうね。
そのための研鑽であって。
三明亭からしの‟姿即心”(姿すなわち心?)は、その姿(所作)で観客の心を掴むのですが、その裏では相当な努力があった事が分かるんですよね。ひかるに話していたのは嘘っぱちで、からしはあかねに真っ向から芸で挑んでいたのです。
これは面白いですよね!
そして歌舞伎を演目の中に忍ばしている事にも大きな意味が出て来ます。落語もまた‟型”を重んじる芸能。ただしブギウギ真田の言うような「歌舞伎の落語化」でもないんでしょう。もう歌舞伎そのものなんじゃないかな?
演目「猿まね」とは
今からしが演っているのは歌舞伎そのものであって、歌舞伎を落語化した‟芝居噺”のようなものではないのかも。観客は実際に「義経千本桜」のワンシーンを見せられているも同じ。三明亭の型によってね。
それを面白くするには、しっかりした歌舞伎の所作ができてこそ。ちゃんと本物の‟型”を見せていなければ成立しない芸。そして定吉の猿真似だってキチンとした‟型”が存在しており、それはそれで演じきれなければ面白くならない。
こういう事のような気がします。
現代の話を古典落語で、また歌舞伎と落語の融合… これほどまでに自由な表現方法が取れるのは落語ならでは。これこそが第170席の「何故其れを落語でやるの?」というブギウギ真田の問いへのアンサーにするのかなぁ。
どうだろうか?
擬古典に乗せる強い想い
控室でしょうか、水瀬花恵が三明亭からしの高座を見つめながら思い出す事がありました。それは「もっと毒っ気や今っぽさを盛り込んだ方が笑いどころ作れそうなのに」というもの。どうして創作落語なのに古典っぽさにこだわるの?って感じかな。
からしにはからしなりの考えがあって。
ライバル2人(あかね&ひかる)に勝ちに行くのは当然の事として、それだけではないものがあると言います。それが「今 俺が擬古典を」やる理由・意味というものらしいんです。
擬古典に乗せる強い想い──
僕が予想するのは…
「俺が古典になる」って事なのかなぁ。
それはつまり‟七代目”三明亭円相になるということであって、「落語とは儂である」の言葉を受け継ぐ強い意志を持っているんじゃないかな? ライバル2人に勝った未来の話としてね。
それならば、同じく第170席のブギウギ真田による「君にとって落語とは何だい?」の答えにもなるんですよ。「落語とは俺だよ」とね。
三明亭円相師匠もまた了見が掴めなかったんですよね(第170席)。からしと同じで。それなら‟破邪顕正”三明亭円相の名と芸を継ぐのは俺しかいないと考えてそうな気がするんだけどなぁ。円相師匠もまたからしの他にはいないと見出してそうだし。
まとめ
おそらく次回でサゲなんだと思うのですが… どうなんでしょうね。まだ演目の行方がサッパリ分からない状況ですからね。もう少し続きそうな気もするんだけど。
- 三明亭の型とは「外形の極意」
- 内が掴めないのなら外に目を向けろ
- からしの‟姿即心”とは
- 演目「猿まね」は定吉の歌舞伎の猿真似で落とす?
- からしは三明亭円相の名と芸を受け継ぐつもり?
次回が楽しみであります!!
ありがとうございました!!





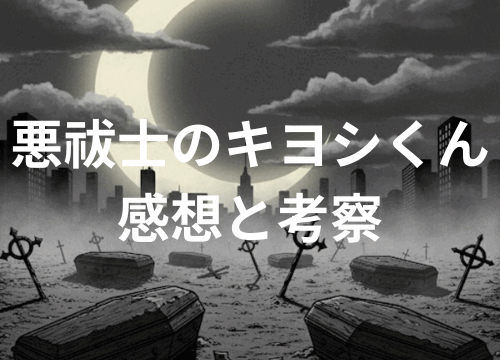

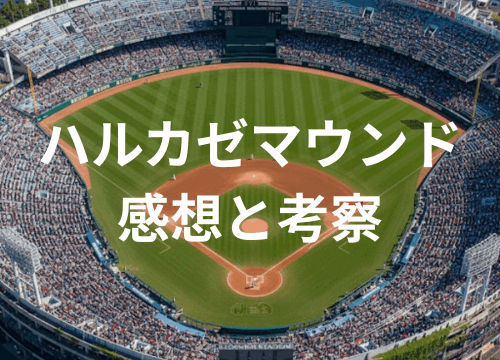


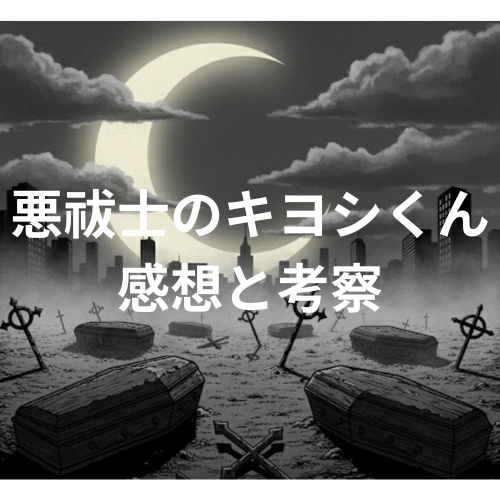

コメント