この記事では、週刊少年ジャンプ2025年40号に掲載された「あかね噺」の第172席「落語バカ」の感想と考察を書いて行こうと思います!
前回の振り返りは下の記事になります!
からしが授けられた三明亭の型とは「外形の極意」であり役ごとに体系化された作法。了見が内から滲むその根源なら、三明亭の型は身体から入って心を掴む‟姿即心”。からしが語る擬古典に乗せる強い想いとは──!?
からしの高座もついにクライマックスです!
言葉は人に拠る
伝統の名の下に押しつけられる修行と言う名の雑務──
それに対する文句は腐る程ある。しかし、それをやり切らないと了見は掴めない。そう思うからこそ三明亭からしは文句を垂れる事なく取り組んでいました。
そんなからしに円相師匠は「貴様は‟了見”は掴めない」と断じたのが第170席でしたね。そして了見と対を成す「三明亭の型」なる極意を授けてもらえる事になるワケですが…
そうではなかったんですね。
言葉は人に拠る
修行と言う名の雑務を文句も言わず取り組んだからこそ、からしは円相師匠から「三明亭の型」を授けてやろうと思ってもらえる弟子になれた。こういう事なんでしょう。
前座修行は人間見習いであり、人としての芯を鍛える時間。
からしは学生時代、授業も聞かずお菓子を食べながらゲームに興じるような人間だったんですよね(第169席)。公式さえ分かればもう授業なんて聞く必要などない。そういう男だった。
しかし落語に公式などなく、攻略法云々どころか理解すら及ばない世界だった。学生時代のようにはいかない。学校の授業と雑務は同列ではないのですが、人生を舐めていた彼にとって必要な時間だったんでしょうね。
そして、この「伝統の名の下に押し付けられる修行と言う名の雑務」を通して ‟伝統”というものが何であるかを知る事になった。からしは第19席の可楽杯本選の高座前、こう言っていたのです。
つまり俺には有んのよ
古典だ伝統だとのたまう輩を
黙らせる自信が!!
‟伝統”は伊達じゃねぇ
修行と言う名の雑務にしてもそう、受け継がれるものには守り続けるだけの意味がある。それによって「三明亭の型」を授けてもらえたワケですからね。円相師匠だってそうやって授けてもらえたのでしょう。
からしが‟古典”や‟伝統”というものが持つ意味を知り、過去の自分の言葉に「分かってねぇなぁ」と言うシーンがあります。それは円相師匠の高座を袖で見ている時なんですね。
客席には沢山の高校生の姿があり、円相師匠の高座を楽しんでいるのが描かれています。からしと同世代どころか、その下の世代に円相師匠の古典落語が刺さっているのが分かります。
そこで古典や伝統が持つ「求められるだけの普遍性」を知る。
これは円相師匠の‟本物の芸”というものに触れたからこそ至る事ができた境地と言えるでしょうか。師匠に「伝統の象徴」たる三明亭円相を選んだ事も大きいような気がしますね。特に深く考えて師匠を選んだワケではなかったんですけど。
擬古典を選んだ理由
意外ね
オリジナルの割には古典っぽいというか
もっと毒っ気や今っぽさを盛り込んだ方が
笑いどころ作れそうなのに
こう水瀬花恵から言われたのを発端に、からしが擬古典をやる理由を語り出すのが前回のヒキでしたね。なぜ彼は擬古典をするのか。
残るモンを作りてぇからだ
演目と重ねて今はまだ「猿まね」なんだけど、伝統の世界に自分の作品を残したい。今はまだ「擬古典」に過ぎないんだけど、自分の作った噺を「古典」と呼ばれるものにしたい。
からしは壮大な夢を持っていたんです!
しかしブギウギ真田のよると、瑞雲大賞の観客は「古典だと疑いもしない… か」と言っているんですね。もうその域まで行っているんです。
それは「観客を信じ込ませる程の深い古典への造詣」があってからこそであって、からしがどれくらい落語に対する強い想いを持っているのかが分かるんですね。とんだ‟落語バカ”とブギウギ真田も褒めています。
次回、‟作品派”である椿家正明師匠がどう講評するのか。
非常に楽しみなんですよね!
からしも「分なら弁えてる」と言っていますし、正明師匠も手放しで褒めるという事はないんでしょう。演目(作品)の評価も審査に入るのかどうか分かりませんけどね。芸の方は非常に高かったハズですから高評価されそうですよね!
2人のライバルにとっての阿良川あかね
からしのとって擬古典をやる理由は、伝統の世界に自分の作品を残したいからというものでした。それは2人のライバル(あかね&ひかる)との勝負とは別のところにあります。その先の夢です。
阿良川あかねに勝つというのが落語家の道に入る動機ではありましたが、今はもうそれだけじゃないんですね。
阿良川ひかるも同じでした。
あかねに勝つためにと落語家の世界に入り、必死に鍛えて来たのですが… 第167席で「でも」と言っているんですよね。もうそれだけで落語をやっていません。その目は客席の方にシッカリ向いていました。
あかねだって2人との勝負はありますが、それだけで瑞雲大賞に出場しているワケではありません。‟志ぐまの芸”に向かって邁進する中での瑞雲大賞なんですよね。そのために正明師匠から「死神」を稽古してもらわなければならない。
おそらく1つの結果が出ます。
勝ち負けがつくのは間違いなさそう。
それを受けて3人の関係性、また3人の落語家としての在り方がどう描かれて行くのか。ここも楽しみな展開になって来ましたね。
まとめ
さぁ次回、からしの得点はどうなるのか!
ひかるを上回るような気がしますが… どうなんでしょうね。とにかく正明師匠の得点ですね。ひかるは86点でした。からしが90点台を叩き出すのかどうかに注目しています!
- 言葉は人に拠る
- 伝統は伊達じゃない
- からしが擬古典をやるのは残るモンを作りたいから
- 2人のライバルと阿良川あかね
次回が楽しみですね!!
ありがとうございました!!





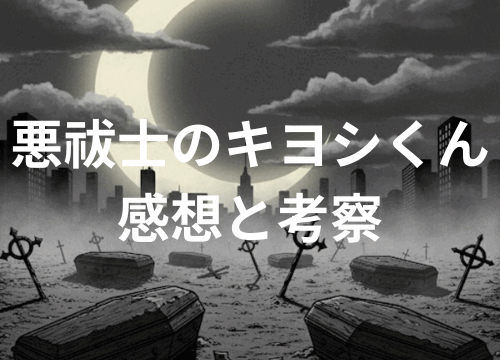

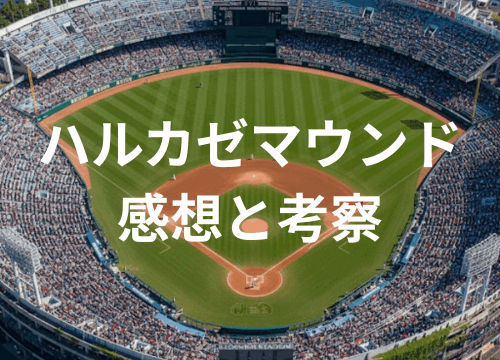

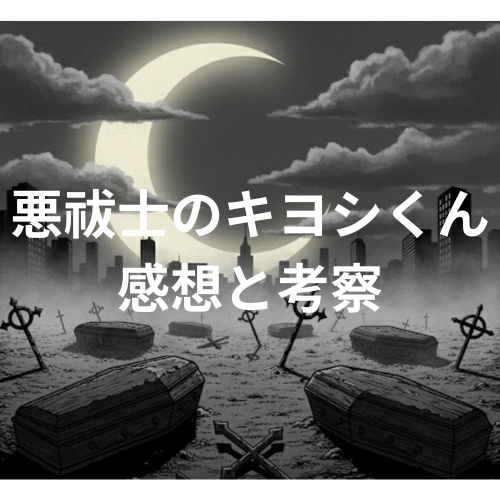

コメント